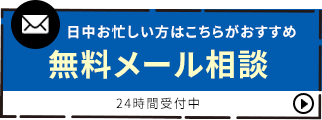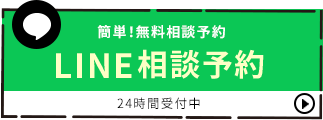高齢になった親の預金管理は、子世代にとって重要な課題の一つです。特に、満期のある定期預金は、管理の手間や急な資金需要への対応という点で、普通預金への移行を検討する方もいるのではないでしょうか。
この記事では、親の定期預金を普通預金に移すための基本的な手続きから、親の状況(元気なうち、認知症が進行している場合、亡くなった後)に応じた具体的な方法、注意点、そしてトラブルを避けるための準備について詳しく解説します。
親の定期預金を普通預金に移すことはできるのか?
親御さんの定期預金を普通預金に移したいという疑問は、多くの方が直面する可能性があります。入院や介護費用の捻出、相続対策、あるいは単に管理の簡便化など、理由は様々でしょう。
結論から申し上げますと、原則として、親御さんご本人の意思確認と手続きを経れば、定期預金を解約し普通預金に移すことは可能です。
しかし、その手続きは親御さんの判断能力の状態や、預金契約の内容によって大きく異なります。安易に進めてしまうと、後々トラブルに発展する可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
①親御さんの判断能力が十分な場合
親御さんの判断能力が十分にあり、ご自身の意思で手続きを行える場合は、比較的スムーズに定期預金を普通預金に移すことができます。
▶必要な手続きの例
- 親御さんご本人が金融機関の窓口へ行く:親御さんの本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)と定期預金の通帳・証書、印鑑を持参し、解約と普通預金への入金手続きを行います。
- 親御さんご本人がオンラインや電話で手続きを行う:金融機関によっては、インターネットバンキングやテレホンバンキングを通じて、定期預金の解約と普通預金への振替が可能な場合があります。ただし、事前に親御さんご本人がこれらのサービスを契約している必要があります。
- 代理人が手続きを行う場合:親御さんご本人が窓口に行けない場合、代理人が手続きを行うには、原則として親御さんご本人の署名・捺印のある委任状と、代理人の本人確認書類、親御さんの本人確認書類、定期預金の通帳・証書、届出印が必要です。委任状の様式は金融機関によって異なるため、事前に確認しましょう。
②親御さんの判断能力が不十分な場合
親御さんが認知症などを患い、判断能力が不十分な場合は、上記のような通常の手続きを行うことが難しくなります。この場合、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
▶成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方を法的に保護・支援する制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人等が、ご本人の意思を尊重しつつ、財産管理や身上監護を行い、日常生活や社会生活をサポートします。類型には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助があります。
委任状作成のポイント
親御さんの定期預金を普通預金に移すための委任状は、金融機関での手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。
不備があると手続きが滞ってしまうため、以下のポイントを押さえて作成しましょう。
▶正確な委任者(親御さん)の情報
親御さんの氏名、住所、生年月日を、金融機関に登録されている情報と一字一句違わず記載します。特に、旧姓やマンション名、部屋番号なども正確に記入しましょう。
▶正確な受任者(代理人)の情報
代理人となる方の氏名、住所、生年月日を正確に記載します。代理人の本人確認書類と記載内容が一致していることが重要です。
▶委任する手続きの明確な記載
どの定期預金を、どのように普通預金に移すのかを具体的に記載します。
▶委任状の作成日
委任状を作成した日付を記載します。金融機関によっては、作成日から一定期間以内のものしか有効としない場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
▶委任者の署名・捺印
親御さんご本人が自署し、金融機関に登録している印鑑を鮮明に押印します。拇印が登録されている場合は拇印が必要です。
▶委任状の有効期限
金融機関によっては、委任状に有効期限の記載を求める場合があります。事前に確認し、必要であれば記載しましょう。
▶金融機関所定の様式の確認
金融機関によっては、独自の委任状の様式を用意している場合があります。事前に金融機関のウェブサイトを確認したり、窓口に問い合わせたりして、所定の様式がある場合はそちらを使用するようにしましょう。
▶親御さんの意思確認
委任状作成にあたっては、必ず親御さんご本人の明確な意思を確認してください。強要や誤解がないように、丁寧に説明し、納得して署名・捺印してもらうことが重要です。
▶代理人の本人確認書類
手続きの際には、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)原本が必要になります。
▶親御さんの本人確認書類
金融機関によっては、親御さんの本人確認書類の提示やコピーの提出を求められる場合があります。
委任状の不備は手続きの遅延につながります。上記ポイントを参考に、正確かつ丁寧に作成するように心がけてください。不明な点があれば、必ず事前に金融機関の窓口に相談しましょう。
親の死後に定期預金を普通預金にできるのか?
親御さんが亡くなられた場合、定期預金は相続財産となり、直ちに親御さんの普通預金に自動的に移行されるわけではありません。
定期預金を相続人の名義に変更したり、解約して現金化したりするためには、相続手続きを行う必要があります。
▶手続きの流れの概要
- 【金融機関への連絡と口座凍結】
まず、親御さんがお取引されていた金融機関に死亡した旨を連絡し、口座の凍結を依頼します。これは、相続財産の保全のために行われる措置です。
- 【相続人の確定と必要書類の収集】
金融機関の指示に従い、相続人を確定するための戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までのもの、相続人全員のもの)や、相続人全員の印鑑証明書、遺言書(あれば)、遺産分割協議書(相続人間で遺産分割協議が成立した場合)など、所定の書類を準備します。必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認が必要です。
- 【相続手続きの申請】
必要書類が揃ったら、金融機関所定の相続手続きの書類に記入・押印し、提出します。
- 【金融機関の審査】
金融機関は提出された書類を審査し、相続人が正当な権利者であることを確認します。
- 【定期預金の解約と払い戻し、または名義変更】
審査が完了すると、定期預金は解約され、相続人の代表口座に払い戻しが行われるか、相続人の名義に変更されます。定期預金を解約して普通預金に移すという形になることが多いです。
▶注意点
- 遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産分割が行われます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定する必要があります。
- 相続人間で遺産分割の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続きが必要になることがあります。
- 相続財産の総額によっては、相続税の申告・納付が必要になる場合があります。
- 相続税の申告・納付には期限(原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)があります。預金の手続き自体に明確な期限はありませんが、放置すると手続きが煩雑になる可能性があるため、早めに進めることが推奨されます。
- 手続きに必要な書類や流れは、金融機関によって若干異なる場合があります。必ず取引のある金融機関に確認するようにしてください。
親御さんの死後の定期預金を普通預金にするには、上記のような相続手続きを経る必要があります。まずは金融機関に連絡し、指示に従って手続きを進めるようにしましょう。ご自身で手続きを行うのが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討ください。
まとめ
親の定期預金を普通預金に移す手続きは、親御さんの判断能力の有無やご存命かどうかによって大きく異なります。元気なうちであれば、ご本人による手続きや委任状による代理手続きが可能ですが、判断能力が不十分な場合は成年後見制度の検討が必要です。
そして、逝去後には相続手続きが必須となります。いずれのケースにおいても、金融機関との連携を密にし、必要な書類や手続きを正確に把握することが重要です。本記事を参考に、ご自身の状況に応じた適切な手続きを進め、スムーズな預金管理にお役立てください。