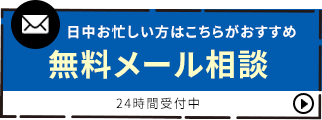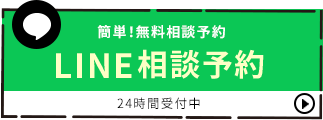近年、「成年後見人制度はひどい」という声を耳にすることがあります。大切な家族の財産や生活を守るための制度であるはずなのに、なぜそのような不信感や批判が生まれているのでしょうか。
この記事では、成年後見人制度が抱える問題点や、実際に起こりうるトラブル事例を深掘りします。その上で、制度を賢く利用するための注意点、万が一トラブルが発生した場合の対処法、そして成年後見制度以外の選択肢についても詳しく解説します。
この記事を読むことで、あなたは成年後見制度の現状を正しく理解し、後悔しないための最適な判断ができるようになるでしょう。
「成年後見人制度がひどい」と言われる理由
「成年後見人制度はひどい」と感じる人がいる背景には、いくつかの要因が考えられます。ここでは、よくあるトラブル事例とその原因、そして制度そのものが抱える問題点について解説します。
よくあるトラブル事例
成年後見人制度を巡っては、残念ながら以下のようなトラブルが後を絶ちません。
- 成年後見人による財産の使い込み・横領
- 不適切な財産管理
- 本人の意向を無視した決定
- 親族間の対立
- 高額な報酬
- 後見人とのコミュニケーション不足
- 後見人のなり手不足
トラブル事例はなぜ起こるのか
これらのトラブルは、個々の後見人の倫理観や専門性の問題だけではなく、制度そのものが内包するいくつかの要因によって引き起こされることがあります。
▶後見人の選任基準の曖昧さ
誰が後見人に適任であるかの明確な基準がなく、必ずしも専門家や適切な人物が選ばれるとは限りません。
▶監督体制の限界
家庭裁判所による後見監督が行われますが、その頻度や内容には限界があり、不正行為を完全に防ぐことは困難です。
▶本人の判断能力の低下
本人の判断能力が低下しているため、後見人の行為を十分に監視したり、異議を唱えたりすることが難しい場合があります。
▶情報公開の不足
後見人の活動内容や財産管理の状況が、本人や家族に対して十分に開示されないことがあります。
制度上の問題点(財産管理・本人の意思反映など)
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の財産管理や身上監護を支援する重要な仕組みですが、以下のような問題点も指摘されています。
▶硬直的な財産管理
本人の状況やニーズに合わせた柔軟な財産管理が難しい場合があります。
▶本人の意思決定の尊重
本人の残された意思や希望が十分に尊重されないことがあります。
▶身上監護の範囲
医療や介護に関する決定など、身上監護の範囲が曖昧な場合があります。
▶手続きの煩雑さ
後見開始の申し立てや、その後の手続きが煩雑で、時間や費用がかかることがあります。
▶専門職後見人の偏り
弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任されるケースが多く、親族が後見人になりにくい傾向があります。
成年後見制度を利用する際の注意点
成年後見制度の利用を検討する際には、上記のような問題点を踏まえ、慎重に進める必要があります。後悔しないために、以下の点に注意しましょう。
後見人は慎重に選ぼう
後見人選びは非常に重要です。以下の点を考慮し、慎重に候補者を選定しましょう。
人柄や誠実さ、倫理観などを十分に確認しましょう。
本人の性格、価値観、生活状況などを理解し、尊重してくれる人物を選びましょう。
適切な財産管理を行うための知識や経験があるか確認しましょう。
本人や家族と円滑なコミュニケーションを取れる人物を選びましょう。
必要に応じて、専門的な知識や経験を持つ専門家を候補に入れることも検討しましょう。
監督制度とその限界も理解しよう
家庭裁判所による後見監督がありますが、その機能には限界があることを理解しておきましょう。
- 後見人には定期的に財産状況や事務報告を行う義務がありますが、形式的なチェックになりがちです。
- 不正行為が発覚するまでに時間がかかることがあります。
- 必要に応じて監督人が選任されますが、費用がかかる場合があります。
「制度を利用しない」という選択肢も視野にいれよう
成年後見制度以外にも、判断能力が不十分になった方を支援する制度や方法があります。安易に後見制度を選択するのではなく、他の選択肢も検討してみましょう。
- 親族が協力して財産管理や身上監護を行う。
- 福祉サービス利用援助や金銭管理の援助を受ける。
- 地域における高齢者やその家族の総合的な相談窓口。
成年後見制度の利用にあまりメリットがない人は、たとえば以下のようなケースです。
▶判断能力が比較的保たれている場合
日常的な判断や意思決定が概ね可能であり、重要な決定についても周囲の支援があれば理解できる程度の方には、任意後見制度や財産管理委任契約など、より柔軟な方法が適している可能性があります。
▶親族や信頼できる支援者が十分にいる場合
親族など、ご本人の意向を尊重し、適切な財産管理や身上監護を無償で行ってくれる方がいる場合、成年後見制度の利用は手続きや費用面で負担となることがあります。ただし、親族間の対立が懸念される場合は、第三者後見人の選任も検討されます。
▶本人の意思が明確である場合
特定の財産管理や身上監護について、ご本人の明確な意思があり、それを尊重してくれる支援者がいる場合、成年後見制度による一律的な保護よりも、個別の契約や支援の方がご本人の意向に沿えることがあります。
成年後見人制度によるトラブル発生時の対処法
もし、成年後見人によるトラブルが発生してしまった場合、放置せずに適切な対応を取ることが重要です。
成年後見人の解任・変更手続き
後見人に不正行為や不適切な行為が見られる場合、家庭裁判所に後見人の解任や変更を申し立てることができます。法的な手続きが必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。
不正行為や不適切な行為を示す具体的な証拠を集めることが重要です。
まずは家庭裁判所に相談し、手続きの流れや必要書類について確認しましょう。
相談できる機関とサポート体制
成年後見制度に関する悩みやトラブルについて相談できる機関はいくつかあります。
| 家庭裁判所 | 後見制度に関する手続きや相談に対応しています。 |
| 弁護士会・司法書士会 | 法律の専門家として、相談や手続きのサポートを行っています。 |
| 成年後見センター・相談支援機関 | 制度に関する情報提供や相談支援を行っています。 |
| 地域包括支援センター | 高齢者やその家族の総合的な相談窓口として、情報提供や関係機関との連携を行っています。 |
後悔しないために知っておくべき代替制度
成年後見制度以外にも、判断能力が不十分になった方を支援する制度や方法があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合わせて最適な選択肢を検討しましょう。
①任意後見制度
任意後見制度とは、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかを、ご自身で事前に決めておく制度です。ご本人が選んだ方(任意後見人)との間で、財産管理や身上監護に関する契約(任意後見契約)を公正証書で結びます。
任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人が選任されることによって効力が生じます。任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に基づいて適切に事務を行っているかを監督する役割を担います。
②家族信託
家族信託とは、ご本人が元気なうちに、ご自身の財産(不動産、預貯金など)の管理・処分・承継について、信頼できる家族(子、配偶者、親族など)に託し、その家族がご本人のために、またはご本人が亡くなった後の利益を守るために財産を管理・運用する仕組みです。
信託契約によって、誰が財産を託す人(委託者)、誰が財産を管理する人(受託者)、誰が利益を受け取る人(受益者)となるかを自由に決めることができます。
【家族信託のメリット】
財産の管理・運用・承継について、ご本人の意思を反映した柔軟な設計ができる点、認知症などで判断能力が低下した後でも、事前に決めた内容に従って財産管理を継続できる点、相続対策にも活用できる点などです。
【家族信託のデメリット】
身上監護には対応できない点、契約内容によっては受託者の負担が大きくなる可能性がある点、信託契約の設計に専門知識が必要となる点などが挙げられます。
③生前贈与
生前贈与とは、ご本人が生きているうちに、ご自身の財産を家族や близкие друзья などに無償で譲り渡すことです。相続財産を減らすことで相続税対策になったり、特定の財産を特定の相手に確実に渡したい場合に有効な手段です。
【生前贈与のメリット】
相続財産を減らすことによる相続税対策、特定の財産を特定の相手に確実に渡せること、受贈者の生活資金の援助などが挙げられます。
【生前贈与のデメリット】
贈与額によっては高額な贈与税が発生する可能性がある点、贈与後に贈与者の生活資金が不足するリスクがある点、判断能力が低下した後は原則として贈与ができなくなる点などが挙げられます。
まとめ
成年後見人制度は、判断能力が不十分になった方を守るための大切な制度ですが、残念ながらトラブルも存在します。「ひどい」と感じる背景には、制度の構造的な問題や、後見人の倫理観、監督体制の限界など、様々な要因が絡み合っています。
しかし、制度の問題点を正しく理解し、注意すべき点を把握することで、トラブルを未然に防ぎ、制度を有効に活用することも可能です。
もし、現在すでにトラブルに巻き込まれている場合は、一人で悩まずに、家庭裁判所や弁護士会、成年後見センターなどの専門機関に相談してください。
そして、将来のために、成年後見制度だけでなく、任意後見制度や家族信託など、他の選択肢についても検討しておくことが大切です。
この記事が、あなたが成年後見制度について正しく理解し、後悔のない選択をするための一助となれば幸いです。