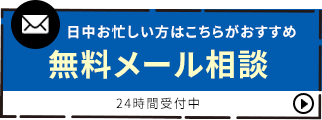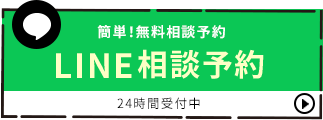故人が遺言書を残していない場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議とは、読んで字のごとく、遺産分割の方法と相続の割合を決める話し合いのことです。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、故人名義の預貯金口座の解約や、不動産の名義変更を行うには、相続人全員の同意が前提となります。
したがって、相続人の一人と連絡が取れない場合は、相続人全員が参加する「遺産分割協議」を行うことができず、故人名義の預貯金口座の解約や、不動産の名義変更などのいわゆる相続手続を行うことができなくなってしまいます。
今回の記事では、相続人の一人と連絡が取れない場合の対処法について、連絡が取れない原因別に解説させていただきます。
原因別:相続人の一人と連絡が取れない場合の対処法
住所や連絡先がわからず連絡が取れない場合(国内居住)
住所や連絡先がわからず、相続人の一人と連絡が取れない、且つその相続人が日本国内にいる前提の場合です。
その場合は、区役所で戸籍の附票を取得し、それで住所を確認した上で、その住所へ手紙を送るなどして連絡を試みるという方法があります。
通常、戸籍の附票を取得できるのは、①本人、②配偶者、③直系尊属(両親や祖父母)、④直系卑属(子や孫)のみであり、①~④以外の方が戸籍の附票を取得するためには委任状が必要です。
しかし、相続が発生している場合には、相続人は他の相続人の戸籍の附票を取得することができます。
住所や連絡先がわからず連絡が取れない場合(海外居住)
住所や連絡先がわからず、相続人の一人と連絡が取れない、且つその相続人が海外にいる可能性がある場合です。
その場合は、外務省に「所在調査」を依頼し、海外の住所や連絡先を調査してもらい、住所や連絡先が判明後に連絡を試みるという方法があります。
外務省が実施する「所在調査」とは、長期に渡ってその所在が確認されていない日本人の連絡先等を配偶者か三親等内の親族からの依頼によって、調査する行政サービスです。
相続人から応答がなく連絡が取れない場合
相続人の住所や連絡先はわかっているが、その住所へ手紙を送ったり、電話をしても意図的に応答がない場合です。なんらかの事情により、こちらから連絡を試みてもまったく応答がないという事態は相続において珍しいことではありません。そのような場合の対処法としては大きく分けて2つです。
1つ目:弁護士に依頼する
弁護士から代わりにその相続人へ連絡を取ってもらい、遺産分割協議を行います。弁護士からの連絡であれば、対応しなければならないと考え、何かしら応答が期待できます。
2つ目:遺産分割調停の申立を行う
遺産分割調停とは、当事者のみで遺産分割協議をすることが難しいような場合に、家庭裁判所の力を借りて、遺産分割協議の成立を目指すものです。遺産分割調停の申立がされると、家庭裁判所から各相続人へ調停開催日の通知が出されることになりますが、何度も調停に不参加の相続人がいるなどして、遺産分割協議がまとまらず調停不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産分割協議の内容を審判(決定)することになります。
行方不明で連絡が取れない場合
周りの誰もその相続人の連絡先を知らず、戸籍の附票で確認した住所に手紙を送っても「宛所に尋ねあたりません(=宛所の住所に住んでいない)」として、手紙が戻ってきてしまい、所在がまったくわからないような、いわゆる行方不明の場合です。そのような場合の対処法としては大きく分けて2つです。
1つ目:不在者財産管理人選任の申立を行う
不在者財産管理人選任の申立とは、不在者財産管理人と呼ばれる、行方不明の人間に代わってその方の財産を管理・保護する人間を家庭裁判所に選んでもらう手続です。
不在者財産管理人選任後、行方不明の相続人に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、話し合いを行います。
※厳密には不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する前提として、家庭裁判所から権限外行為許可を得る必要があります。
なお、不在者財産管理人を選任した場合、行方不明の相続人には最低限法定相続分(民法で示された遺産分割の割合)を確保する必要があったり、弁護士など専門職が不在者財産管理人に選任された場合は予納金が必要になったりする点には注意する必要があります。
2つ目:失踪宣告の申立を行う
失踪宣告とは、ある人間が長期間行方不明になっていて、生死が不明である場合に限り、その生死不明の人間を法律上死亡したものとみなす効果を発生させるよう家庭裁判所に求める手続です。失踪宣告が受理されると行方不明だった相続人は法律上死亡したものとみなされるため、その人間を除外して遺産分割協議を行うことができます。ただし、行方不明だった人間に相続人がいる場合はその方が新たに遺産分割協議に参加することになります。
失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があり、普通失踪の場合は、生死不明の期間が7年以上、特別失踪の場合は、事故や災害など死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去ってから生死不明の期間が1年以上の場合に申立が可能です。
弊所では、失踪宣告の申立のサポートも行っておりますので、よろしければ下記リンクをご覧ください。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、相続人の一人と連絡が取れない場合の対処法について解説しましたが、連絡が取れない原因ごとに取るべき対処法というのは異なり、適切な判断をすることは難しいです。
また、遺産分割調停の申立や不在者財産管理人選任の申立、失踪宣告の申立などの手続きは煩雑な部分も多いため、相続人の一人と連絡が取れない場合は一度弊所のような専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。