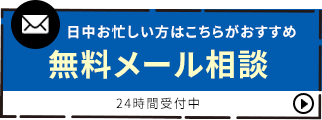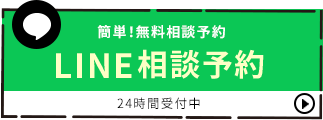「相続登記は自分でできる?なるべく費用を浮かせたいんだけど…」
「周りに自分でやったという知りたいがいる、自分もできそうな気がするけど、実際どうなんだろう?」
相続登記は2024年に義務化され、多くの方の悩みの種です。専門家に依頼するにもお金がかかり、遺産の内容によっては赤字になることもあります。
結論をお伝えすると、相続登記を自分で行うことは可能です。ただし、現実的な場合とそうでない場合があります。
本記事では、相続登記を自分で行う時の方法・必要書類はもちろん、自分でできるかどうかの判断基準についても解説します。
相続の状況や、メリット・デメリットを比較し最良の方法を選べるようにするため、まずは知識を身につけていきましょう。
相続登記を専門家に依頼せず自分で行うことは可能
相続登記は、不動産の遺産を相続した場合に必要になる名義変更手続きです。2024年から義務化され、自分もしくは専門家(司法書士・弁護士)に依頼し行う必要があります。
相続登記を専門家に依頼をすると、一般的には10〜15万円程度の金額が発生するため、自分で行いたいと考える方も多いのが現状です。
法律上は自分で行っても問題なく、実際に調べながら相続登記を行った事例も多々あります。しかし、相続登記はシンプルなケースと複雑なケースがある点にご注意ください。
次の項目では、自分で相続登記を行えるケースと、専門家に相談した方がいいケースを紹介します。
また、前提として自分で相続登記を行う場合は、平日の日中に時間が取れる方に限られます。法務局や役所とのやり取りが多く、日中しか空いていないためです。
相続登記を自分で行えるケース・難しいケース
ここでは、相続登記を自分で行えるケースと、専門家に依頼した方がいいケースを紹介します。専門用語については本文でわかりやすく解説しておりますので、当てはまるケースかどうかの参考にしてください。
自分だけでも相続登記に挑戦できるケース
相続の内容がシンプルなケースなら、自分で調べながら相続登記が可能です。
- 法定相続人通りに相続するケース
- 遺言で相続内容が明確に決まっているケース
- 相続人全員がすぐに集まれるケース
1.法定相続人通りに相続するケース
法定相続人通りに相続する場合は、最もシンプルに相続手続きを進められます。法定相続とは、法律で定められた相続人に、定められた割合の遺産を相続する方法です。
遺言がない場合や、遺産分割協議を行わない場合、相続放棄をする人がいない場合に、法定相続が発生します。
被相続人(故人)の配偶者・子どもの有無で割合は変わりますが、調べながら進められる範囲です。
2.遺言で相続内容が明確に決まっているケース
遺言書があり、相続内容が明確に決まっているケースも自分で相続登記できる可能性が高いです。
ただし、遺産目録が全て記載されていない場合や、分割の割合が指定されていない遺産がある場合などは手間が大きくなります。この場合は、専門家でなければ難しくなるケースもあるためご注意ください。
3.相続人全員がすぐに集まれるケース(特に遺産分割協議を行う場合)
相続人全員がすぐに集まれるケースも、自分で相続登記しやすいケースです。特に、遺産分割協議という、相続人(遺産を受け取る人たち)で話し合い、割合を決める方式を取る場合重要になります。
相続人全員の印鑑が必要な場合や、それぞれが書類を記載する場面も多いため、遠方の親戚がいる場合は現実的でないケースが多いです。
専門家に依頼した方がいいケース
専門家に依頼した方がいいケースは、相続登記が複雑になるケースです。具体的には、以下のような場合は専門家への相談を強く推奨します。
- 代襲相続が発生するケース
- ご先祖名義のまま放置されていた不動産
- 相続人同士が不仲で、手続きが円滑に進まないケース
- 代償分割・換価分割を行いたいケース
1.代襲相続が発生するケース
被相続人から見て、子が亡くなっており孫に代襲相続する場合は、専門家に依頼した方がいいケースです。
代襲相続が発生すると、二世代、三世代に渡り相続関係を調査しなければならず、その分手間と確認の時間が増えてしまいます。
2.ご先祖名義のまま放置されていた不動産
相続する不動産が、ご先祖名義のまま放置されていたものの場合、手続きが複雑になります。
相続登記が義務化になったのは、2024年からなため、それ以前の不動産には相続登記されていないものもあります。自分で相続登記を行うか検討する場合は、不動産の名義が被相続人(故人)になっていることを確認しましょう。
3.相続人同士が不仲で、手続きが円滑に進まないケース
相続人同士が不仲であり、手続きに時間がかかる場合も専門家に依頼することをおすすめします。
必要な部分は専門家が代行して連絡、書類のやり取りを行いますので、そりが合わない親族と無理に顔を合わせることがありません。
4.代償分割・換価分割を行いたいケース
代償分割・換価分割を行いたい場合も専門家に相談しましょう。
代償分割とは、不動産を相続する代わりに、所有する財産を他の相続人に譲渡することです。換価分割とは、遺産を売却して換金し、その代金を分配する方法です。
いずれも通常の相続登記に比べ多くのステップが増えるため、専門的な知識と労力がかかります。
相続登記を自分で行う2つのメリット
相続登記を自分で行うメリットは大きく2つあります。
- 相続にかかる費用を「10〜15万円」削減できる
- 相続・登記の知識がつく
1.相続にかかる費用を「10〜15万円」削減できる
相続登記を自分で行う最大のメリットは、費用を軽減できることです。依頼先にもよりますが、10〜15万円の軽減になるケースが多いです。
依頼先に料金確認をしなくていい、報酬の変動による高額請求される心配がないなど、費用に関する心理的なメリットもあります。
2.相続・登記の知識がつく
相続・登記に関する知識がつくのもメリットの一つです。親族が多く相続の機会が多い場合や、不動産投資をしており登記が必要な場合など、知識があればスムーズに進行できる場面が多々あります。
また、ファイナンシャルプランナーや司法書士など、相続に関する職に就きたい人は実際のモデルケースとして行えるため、大きなメリットになります。
相続登記を自分で行う2つのデメリット
相続登記を自分で行う場合、デメリットの方が大きくなることもあります。具体的には以下の3点がデメリットです。
- 時間と手間がかかる
- 登記漏れなどのリスクが高い
1.時間と手間がかかる
詳しくは後述しますが、相続登記を行う場合揃える資料の数が膨大な量になります。請求してから手元に届くまで時間がかかるものもあり、提出後も修正などで時間が取られるケースが多いです。
また、役所・法務局とのやりとりも綿密に行わなければなりません。間違いがある場合は都度修正し、再提出を繰り返すことになります。平日の日中に電話が来ることがほとんどなため、時間に融通の利く状況でなければ手間と時間がかかります。
相続時は相続税の申告期限や葬儀の手配、死亡届の提出など多忙になります。自分で行う場合は、現実的に可能か一度シミュレーションしてから判断しましょう。
2.登記漏れなどのリスクが高い
登記漏れなどのリスクが高いのも、大きなデメリットです。登記漏れをすると、登記時の方法を遡り、ミスを修正しなくてはなりません。書類は一部使い回しができますが、年度が異なる場合は評価証明書など再度取得が必要になる書類もあります。
また、取得を知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料に処される点にも注意が必要です。(正当な理由がない場合に限る)
過料があった場合、専門家への依頼料と変わらない金額になってしまうため、安全性を重視して依頼する方も多くいらっしゃいます。
自分で相続登記をする時の流れ
自分で相続登記を行う場合、以下の流れで実施します。
- 登記事項証明書で不動産の状況を確認する
- 戸籍謄本で相続すべき人を調べる
- 必要な書類を集める
- 遺産分割協議書を作成する(遺産分割協議を行う場合のみ)
- 登記申請書を作成し、提出する
1.登記事項証明書で不動産の状況を確認する
まず、登記事項証明書を取得して、相続する不動産を確認します。特に重要になるのが名義であり、被相続人ではなくご先祖様名義になっている場合は手続きが複雑になります。
登記事項証明書は、法務局のサイトからオンラインで申請でき、窓口や郵送での受け取りが可能です。早めの段階で申請し、確認しておきましょう。
2.戸籍謄本で相続すべき人を調べる
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を調べ、相続すべき人を調べます。基本的には法定相続人の人数と分割の割合を確認しておきましょう。
ただし、遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されるためご注意ください。
3.必要な書類を集める
不動産の状況の確認が終わり、相続人が決定した後は必要な書類を集めます。必要な書類は後述しますが、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書が必要になるため、早めの段階で周知しておきましょう。
4.遺産分割協議書を作成する(遺産分割協議を行う場合のみ)
遺産分割協議を行う場合は、法定相続人全員で集まり、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成するために、相続人全員分の署名と実印が必要になるためご注意ください。
5.登記申請書を作成し、提出する
書類が全て揃ったなら、登記申請書を記載し法務局へ申請します。
注意が必要な点としては、相続人の居住地ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要な点です。
申請の方法は、窓口・郵送・オンラインと3つの方法があります。オンライン申請の場合は電子署名及び電子文書が必要になるため、事前に確認しておきましょう。
自分で相続登記をするために必要になる書類
ここでは、相続登記をするために必要になる書類を紹介します。
必ず必要になる書類
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 |
| 不動産取得者の住民票 | 市区町村役場 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 |
| 収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
| 登記申請書 | 自分で作成 |
| 返信用封筒 | コンビニ・100均など |
上記がどの相続時にも必ず必要になる書類です。数が多いため、早い段階で申請し手元に集めておきましょう。
遺産分割協議をする場合必要になる書類
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 自分で作成(相続人全員の署名が必要) |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 |
遺産分割協議を行う場合は、追加で上記の書類が必要になります。相続人全員分の署名・印鑑証明書が必要なため、集まる前に周知しておき漏れがないようにしましょう。
遺言書によって、法定相続人以外が相続する場合の書類
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 遺言書 | 自筆証書遺言の場合は自宅公正証書遺言の場合は公証役場 |
| 遺言執行者の印鑑証明書(遺言書に執行者の記載があった場合) | 市区町村役場 |
| 遺言執行者選任審判謄本(家庭裁判所で執行者が選任された場合) | 家庭裁判所 |
| 相続人の印鑑証明書(遺言執行者が選任されていない場合) | 市区町村役場 |
遺言書がある場合、法定相続人以外の相続について記載されている場合があります。その場合は遺言書が優先され、上記の書類が追加で必要になることを覚えておきましょう。
特に遺言執行者が選任されているかどうかで、必要になる書類が変わる点にご注意ください。
確実な相続登記をしたい場合は、札幌大通遺言相続センターへご相談ください
相続登記は、シンプルなケースの場合自分で行っても問題が起こりにくいです。しかし、複雑なケースであるほど専門的な知識が必要になります。
登記の記載を間違えてしまうと、遡っての確認や再度書類の集め直しなど、多くの手間が発生してしまいます。スムーズに相続登記を進めたい、確実に登記簿を記載し安心して相続したい方はぜひ札幌大通遺言相続センターへご相談ください。
札幌大通遺言相続センターでは、相続登記から相続の丸ごとサポートまで、幅広いサービスを実施しています。なるべく費用を抑えたい方は33,000円〜の「不動産の名義変更サポート」がおすすめです。
複雑な相続登記を一括して代行、書類の収集や遺産分割協議書の作成などもお手伝い致します。
お客様の費用に合わせて、柔軟な対応をさせていただければと存じますので、まずは無料相談にてお気軽にご相談ください。
まとめ
相続登記は、シンプルな相続の場合、自分で行うことも可能です。ただし、代襲相続が発生する場合や不動産の名義が被相続人以外の場合などは複雑になるため、専門家への依頼をおすすめします。
相続登記を自分で行えば10〜15万円ほどの費用を削減できます。しかし、時間と手間がかかり、登記漏れのリスクもありますのでデメリットも考えたうえでご検討ください。
相続登記には多くの書類と、確認事項があります。自分で登記する場合は一つひとつ確認しながら行いましょう。
専門家に依頼する場合は、必要書類の取得から書類の作成・提出まで代行してくれる事務所を選ぶことをおすすめします。
札幌大通遺言相続センターでは相続登記に関するお役立ち情報を多く公開しています。以下のページから一覧でご覧になれますので、ぜひ参考にしてください。