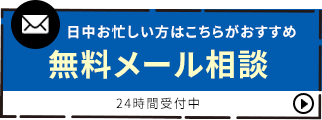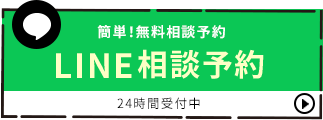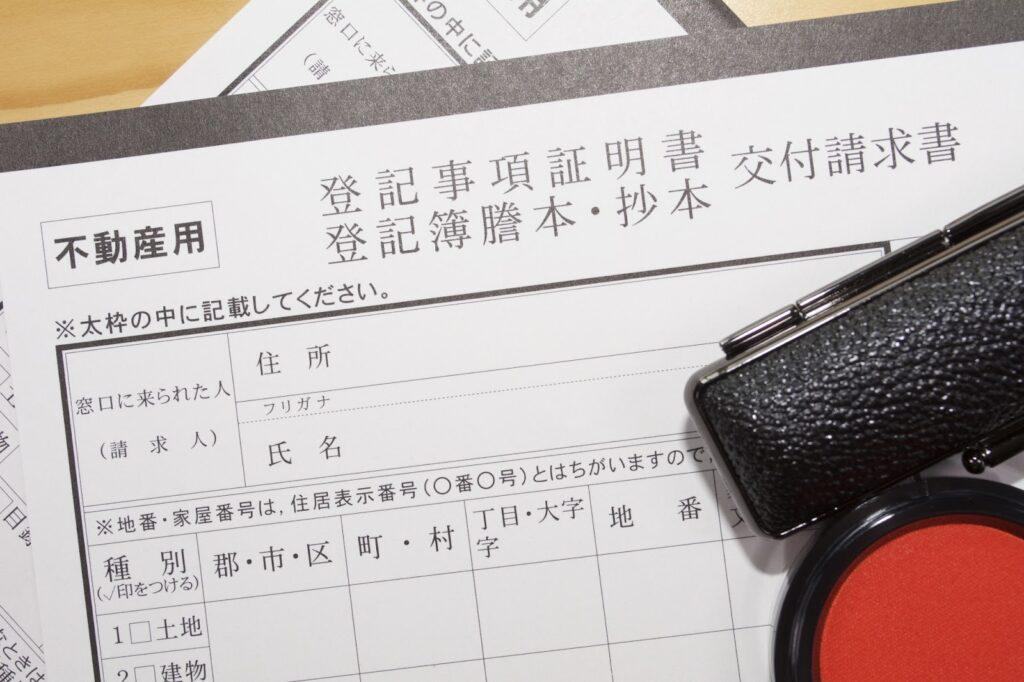
2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。放置すると10万円以下の過料が課される可能性があるため、早めの対応が重要です。
この記事では、相続登記とは何か、なぜ義務化されたのか、必要書類、自分で行う場合の手順、司法書士に依頼するべきケース、費用、選び方などを詳しく解説します。
相続登記とは土地・建物の名義変更のこと
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。土地、家、マンションなどの不動産が対象となります。
相続登記を先延ばしにすると、こんなトラブルが待っている!
相続登記は、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する大切な手続きであり、先延ばしにしてしまうと、後々深刻なトラブルに発展してしまう可能性があります。
1. 遺産分割協議がうまくいかず「争続」に至る
相続人が複数人である場合は遺産分割協議を行い、相続登記を行う必要があります。遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を話し合うことです。
しかし、遺産分割協議をせず相続登記を放置していると、時間が経つにつれて協議が難航する可能性が高くなります。その理由は以下のとおりです。
- 相続人が増える:時間とともに新しい相続が発生し、相続人が増えると、協議の人数が増え、意見調整が難しくなります。
- 人間関係が複雑化する:相続人が増えると、親族間の人間関係も複雑になり、円満な協議が難しくなります。
上記のように、相続登記を放置することで、遺産分割協議が長引いたり、まとまらなかったりする可能性が高くなります。最悪の場合、裁判に発展するケースも考えられます。
2. 不動産の差し押さえの恐れがある
遺産分割協議で不動産の取得を決定しても、相続登記を行わないと、他人から不動産を差し押さえられてしまう可能性があります。
共同相続人の誰か1人が借金を抱えている場合、債権者は相続人に代わって法定相続による相続登記を申請し、借金を抱えている相続人の持分を差押登記することができます。
遺産分割協議の結果、借金を抱えている相続人が不動産を取得しないことになっても、先に登記された差押は取り消されません。
この事態を避けるためには、相続登記を早急に行うことが重要です。
3. 不動産の売却が困難になる
相続登記を行わないで家や土地を売却しようとすると、不動産会社から「相続登記が済んでいないのですぐには売れない」と指摘を受けることがあります。
これは、不動産の売却には相続人への名義変更が完了している必要があるためです。
相続登記が完了していない場合、売却手続きが遅延したり、売却価格が下落したりする可能性があります。
4. 公的書類の発行が困難になる
相続登記には、関係者の戸籍謄本や住民票の除票など公的書類が必要です。しかし、相続登記を放置していると、時間が経つにつれてこれらの書類を入手するのが難しくなります。
公的書類には保管期限が定められているものがあり、期限を過ぎると廃棄されてしまう可能性があるからです。
相続登記の義務化:2024年4月1日から放置は厳禁!
従来は放置も可能だった相続登記が、2024年4月1日より義務化されました。
この改正により、相続による不動産取得後3年以内に登記を行わない場合は、10万円以下の過料に科される可能性があります。
法改正以前に相続した不動産も対象となるため、早めの対応が重要です。
【ポイント】
- 2024年4月1日より相続登記が義務化
- 不動産取得後3年以内に登記を行わない場合は10万円以下の過料の対象に
- 法改正以前に相続した不動産も対象
相続登記の必要書類
以下に、相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等(法務局の資料より)を参考に、ケース別に「入手書類」と「作成書類」を整理しました。具体的な入手方法については、上記リンクよりご確認ください。
①遺産分割協議の場合
| 入手書類 | |
| 亡くなられた方(被相続人) | 戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍住民票の除票または戸籍の附票 |
| 相続人全人(相続人全員) | 戸籍謄本印鑑証明書固定資産税課税証明書 |
| 法定相続人のうち、新しく所有者になる相続人 | 住民票 |
| 作成書類 | |
| 新しい所有者 | 登記申請書 |
| 新しい所有者と代理人 ※代理人による申請の場合 | 委任状 |
| 法定相続人 | 遺産分割協議書 |
| 新しい所有者 | 相続関係説明図 ※戸籍等の原本の還付を希望する場合 |
②法定相続分の相続の場合
| 入手書類 | |
| 亡くなられた方(被相続人) | 戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍住民票の除票または戸籍の附票 |
| 法定相続人 | 戸籍謄本固定資産課税明細書住民票 |
| 作成書類 | |
| 新しい所有者(相続人) | 登記申請書 |
| 新しい所有者と代理人 | 委任状 |
| 新しい所有者 | 相続関係説明図 |
③遺言書がある場合(法定相続人が相続する場合)
| 入手書類 | |
| 亡くなられた方(被相続人) | 自筆証書遺言or公正証書遺言or秘密証書遺言戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍住民票の除票または戸籍の附票 |
| 新しく所有者になる方 | 戸籍謄本固定資産課税明細書住民票 |
| 作成書類 | |
| 新しい所有者(相続人) | 登記申請書 |
| 新しい所有者と代理人 | 委任状 |
| 新しい所有者 | 相続関係説明図 |
相続登記を自分で行う流れ
1. 相続の対象となる物件の特定と不動産登記簿状況の確認
相続登記を行うには、まず相続登記の対象となる不動産を特定する必要があります。権利証や固定資産税納税通知書を確認する他、名寄帳の取り寄せを行うなどし、漏れの無いようにする必要があります。
対象となる不動産が確定したら、次に登記事項証明書を取得し現在の登記簿の状況を確認します。登記事項証明書は、法務局にて取得することができます。また、オンラインでの閲覧も可能です。
2. 戸籍の収集
相続人が誰であるかを調べ、また証明するために戸籍を収集する必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の現在の戸籍謄本などです。
相続人の中に亡くなっている人がいる場合や相続人が兄弟姉妹である場合には、さらに必要な戸籍が増えます。
3. 遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残していない場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。
【記載事項】
- 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所
- 相続人全員が遺産分割の内容に合意していること
- 相続する財産(ここでは相続する不動産について)
- 相続人全員の氏名・住所
【作成方法】
- 法務局で配布している書式を使用するか、専門家に依頼することができます。
- 相続人全員の実印で捺印し、印鑑証明書を添付します。
3. 法務局での登記申請
必要な書類が揃ったら、申請書を作成して、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。申請書は法務局のHPからダウンロードできます。
また、不動産の名義変更を申請する際には、後述の登録免許税という税金がかかり、こちらの納付を併せて行う必要があります。
登記手続きが完了すると相続した不動産ごとに新たに「登記識別情報通知」、いわゆる権利証にあたる書類が発行されます。これを受け取って、手続きは完了です。
相続登記を自分で行うメリット・デメリットまとめ
1.自分で行うメリット:費用節約
最大のメリットは、司法書士に支払う報酬を節約できることです。相続登記の報酬は、不動産の数や評価額、地域によって異なりますが、一般的には5万円~15万円程度かかります。
自分で行う場合は、この費用を丸々節約できるため、経済的な負担を軽減できます。
2. 自分で行うデメリット:時間と労力
最大のデメリットは、手続きに時間と労力が必要となることです。具体的には、以下の作業を行う必要があります。
- 必要書類の収集:戸籍謄本や住民票など、様々な書類を集める必要があります。
- 必要書類の作成:遺産分割協議書や登記申請書を作成する必要があります。
- 法務局への申請:必要書類と登記申請書を法務局に提出し、手続きを進めます。
これらの作業は、慣れない人にとっては非常に時間と労力**がかかります。平日の日中に時間が取れない方や、役所や法務局への手続きに慣れていない方は、負担が大きすぎる可能性があります。
3. その他のデメリット
- 登記漏れのリスク:被相続人が複数の不動産を所有している場合に、その特定が十分でないと登記漏れのリスクが高くなります。例えば、自宅の他に遠方に土地を所有していた場合や、自宅の前の私道を所有していた場合などがあります。
- ミスによるトラブル:書類作成や手続きにミスがあると、登記が完了しないだけでなく、トラブルに発展する可能性があります。
司法書士に依頼すべき6つのケース
相続登記を司法書士に依頼すべき6つのケースを詳しく解説します。
1.平日に時間がとれない
相続登記を申請する法務局の窓口対応時間は平日9時から17時までです。仕事などで平日の日中に時間が取れない方は、自分で手続きを進めるのは難しいでしょう。
「自分でやるつもりで準備していたけれど、平日に時間が取れず気がついたら1年以上も経ってしまった」と依頼に来る方も少なくありません。
2. 不動産を早く売却したい
相続した不動産を売却して代金を相続人間で分配する場合や、相続税の納税資金を金融機関から借りる場合は、できるだけ速やかに相続登記を行うべきです。
売却時には買主への所有権移転登記、借入時には抵当権など担保権設定登記を行いますが、いずれも前提として相続登記が必要だからです。
3. 相続した不動産が複数ある
亡くなった人が自宅以外に、賃貸マンションや駐車場、山林、田畑など複数の不動産を所有していた場合も注意が必要です。
不動産の所在地が散らばっていて管轄する法務局が分かれる場合には、物件ごとに別々の法務局に申請する必要があります。
4. 相続人に未成年がいる
未成年の相続人がいる場合には、遺産分割協議を行う前提として特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の選任は家庭裁判所への申立てが必要ですが、司法書士は申立書の作成業務を行うことができます。
5. 相続人に認知症の人がいる
認知症等で意思能力が低下してる相続人は適切な判断ができないため、遺産分割協議に参加することができません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となるため、このままでは話し合いをすすめることができません。
このような場合は、認知症の相続人のために家庭裁判所へ後見開始の申立てを行い、後見人を選任してもらう必要があります。この申立書の作成業務についても司法書士へ依頼することができます。
相続登記を司法書士に依頼するおおまかな流れ
- 相談・見積り
- ご依頼
- 必要書類の収集や作成
- 相続人全員の意思確認、遺産分割協議書へご署名・ご捺印
- 相続登記の申請
- 完了書類のお渡し
札幌大通遺言相続センターは初回無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記にかかる費用はおおまかに3つ
相続登記には、大きく分けて3つの費用が発生します。
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
- 戸籍謄本等各種証明書の発行手数料:取得する書類によって異なる
- 司法書士報酬:5~15万円が相場だが、状況によって変動
1. 登録免許税
固定資産税評価額の0.4%がかかります。不動産の価値に基づいて算出されるため、高額な不動産を相続するほど高くなります。
2. 戸籍謄本等各種証明書の発行手数料
戸籍謄本、住民票や印鑑証明書など、手続きに必要な書類を取得する際に発生する費用です。取得する書類によって金額は異なりますが、数千円程度が一般的です。
3. 司法書士報酬
司法書士に依頼する場合にかかる費用です。5~15万円が相場ですが、不動産の個数や相続人の数によって加算されることもあります。
また、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成などの業務は、別途報酬が発生する場合もあります。
司法書士に依頼する前に、見積書や報酬規程を提示してもらい、内容をしっかりと確認することが重要です。
相続登記における司法書士の選び方
1. 相続関係業務の経験が豊富
司法書士の業務は、登記以外にも裁判書類の作成、成年後見、債務整理など多岐にわたります。
その中でも相続登記や遺産整理など、相続手続きに関する業務に特化している司法書士の方が、よりスムーズかつ正確な対応を期待できます。
具体的には、以下のような経験を確認しましょう。
- 相続登記の件数
- 複雑な相続案件の経験
- 相続人との円滑なコミュニケーション実績
2. 他の士業と連携できる
相続登記は、税理士、弁護士、行政書士など他の士業との連携が必要となる場合も多くあります。
例えば、相続登記から派生して相続税申告が必要であれば税理士、相続人間で紛争がある場合には弁護士、許認可の承継がある場合には行政書士というように、それぞれの専門知識を活用する必要があります。
他の士業との連携がスムーズな司法書士であれば、ワンストップで幅広いサポートを受けることができ、手続きの負担を軽減することができます。
3. 複数の司法書士と面談し、相性を確かめる
司法書士との相性は、相続手続きを円滑に進める上で非常に重要です。
相続登記では、ご自身の財産状況や家族関係など、プライベートな情報を共有する機会も多く、数ヶ月間にわたってやり取りすることもあります。
そのため、信頼できる相手を選ぶことが大切です。
複数の司法書士と面談し、以下のような点を比較検討しましょう。
- 説明内容: わかりやすく丁寧な説明をしているか
- 質問への対応: 質問にしっかりと答え、不安を解消してくれるか
- 人柄: 話しやすく、信頼できるか
- 事務所の雰囲気: 居心地が良いか
面談を通して、直感的に「この人なら安心して任せられる」と感じられる司法書士を選ぶことが重要です。
確実な相続登記をしたい場合は、札幌大通遺言相続センターへご相談ください
2024年4月1日より義務化されたため、相続登記は早めの対応が必要です。自分で行う場合は、必要書類や手順をしっかりと確認しましょう。時間や労力がかかると感じる場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
相続登記は、シンプルなケースの場合自分で行っても問題が起こりにくいです。しかし、複雑なケースであるほど専門的な知識が必要になります。
手続きを間違えてしまうと、遡っての確認や再度書類の集め直しなど、多くの手間が発生してしまいます。スムーズに相続登記を進めたい、確実に相続手続きを行いたい方はぜひ札幌大通遺言相続センターへご相談ください。
札幌大通遺言相続センターでは、相続登記から相続の丸ごとサポートまで、幅広いサービスを実施しています。なるべく費用を抑えたい方は33,000円〜の「不動産の名義変更サポート」がおすすめです。
複雑な相続登記を一括して代行し、書類の収集や遺産分割協議書の作成などもお手伝い致します。
お客様の費用に合わせて、柔軟な対応をさせていただければと存じますので、まずは無料相談にてお気軽にご相談ください。